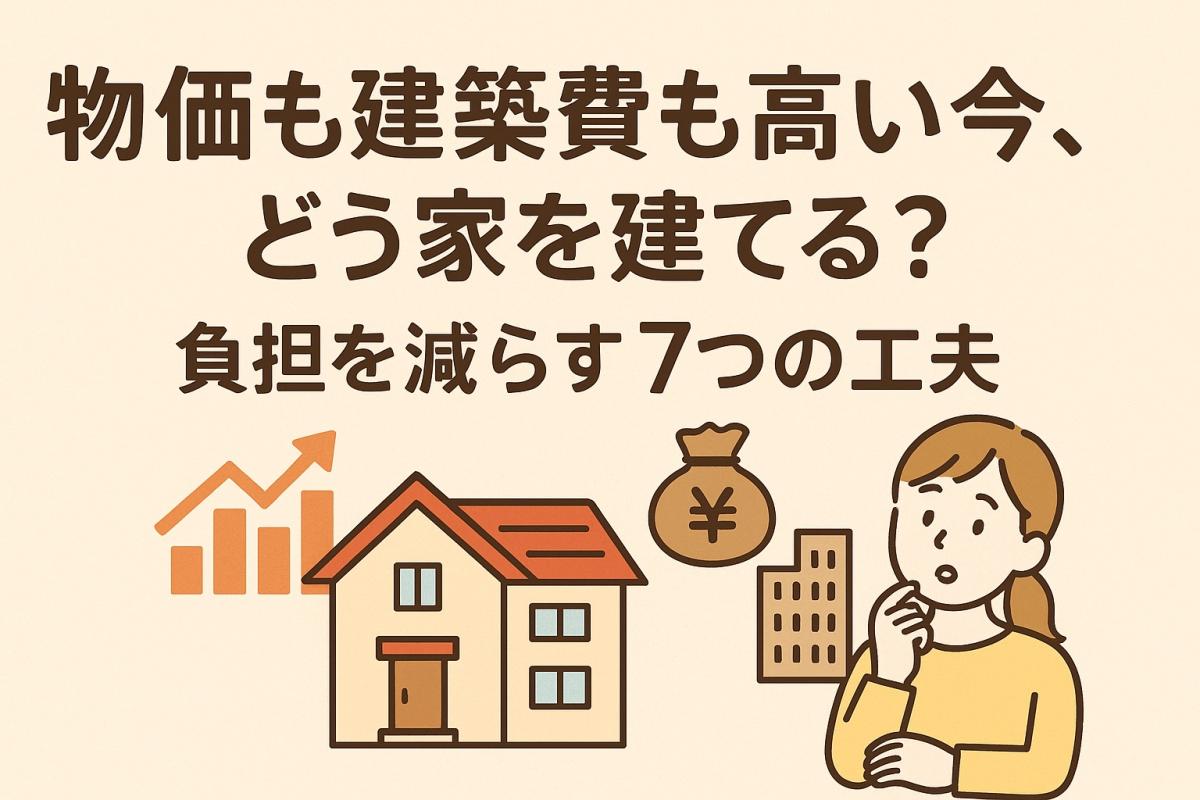
「今、家を建てるのは損じゃないか」「物価も建築費も上がっていて不安」そんな声が家づくりを検討している方々から多く聞かれるようになっています。2025年現在、住宅価格は数年前に比べて上昇しており、とくに建材費や住宅ローン金利の上昇が家計に大きな影響を与えています。土地価格については、東京都心・名古屋・大阪といった都市部では上昇傾向が続いていますが、北設楽郡・新城市・豊川市の地域では比較的安定しています。ただし、建物にかかるコストや金利の負担が増しているため、総合的に見ると住宅取得の負担は以前よりも重くなっています。しかし、それでも“家を持ちたい”という希望をあきらめたくはない方にとって、今こそ必要なのは「正しい知識」と「無理のない工夫」です。今回の記事では、今のような物価高・建築費高騰の時代に家を建てる際、少しでも負担を減らすための7つのポイントをわかりやすく解説します。
Contents
まずは、なぜ家づくりのコストがここまで上がっているのかを整理してみましょう。
ウッドショック(2020年以降の木材供給不足)を契機に、木材価格は一時的に急騰し、その後も安定することなく高止まりの状態が続いています。これは、輸入木材の供給不安、為替レートの変動、物流費の増加など複数の要因が絡んでおり、国産材への需要集中も価格の上昇要因となっています。
また、鉄やコンクリートといった他の建材についても世界的なインフレや原材料価格の上昇、さらにはウクライナ情勢などの地政学的要因(国際的な戦争や対立による影響)によって価格が上昇しています。これらの資材価格の高騰は、住宅建築の原価を押し上げる大きな要因のひとつとなっています。
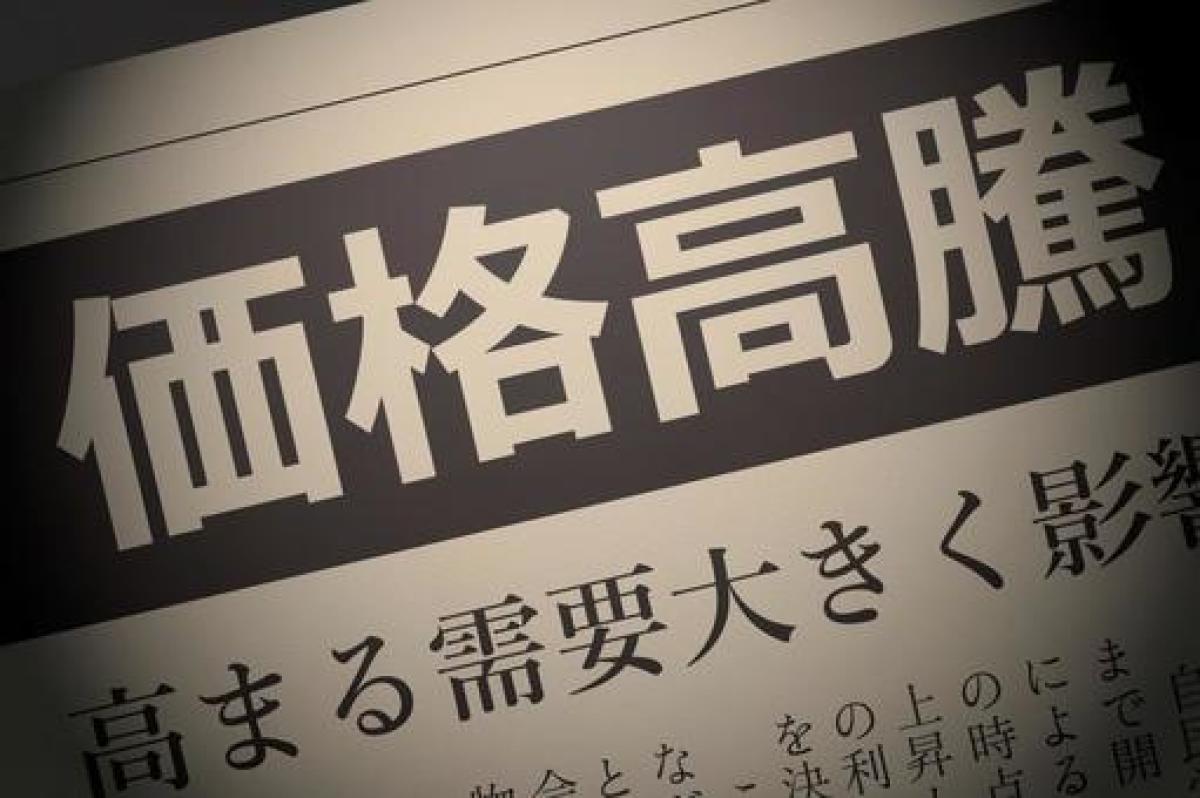
ウッドショック以前の住宅需要が高まっていた時期には職人への発注コストも上昇していました。しかし、近年は建築価格の高騰により新築の着工数が減少し、職人の仕事量も減少傾向にあります。そのため、地域によっては職人への発注コストが上昇していない、もしくは横ばいに近い状況も見られます。ただし、依然として技術者の高齢化や後継者不足といった課題が続いており、将来的な発注コストの上昇リスクは残されています。

電気代・ガス代の上昇や物流コストの増大は建材や設備の製造・輸送コストを押し上げ、間接的に住宅価格全体に影響を与えています。特に燃料費の高騰は工場の生産コストや現場への配送費用にも波及しており、結果として住宅価格に跳ね返ってくる構造です。
これらの要因は国際的なエネルギー需給の不安定さや為替変動、長期的な物価上昇の流れなどが背景にあるため、短期間での改善は見込みづらく、数年単位で継続していく可能性が高いと考えられています。

建築費が上がっているだけでなく、物価高によって普段の暮らしにかかるお金も確実に増えています。家を建てたあとの生活費が膨らめば、住宅ローンの返済計画にも影響を及ぼしかねません。ここでは、特に支出が増えやすい3つの項目を詳しくご紹介します。

物流費や原材料費の上昇、円安などの影響により、スーパーでの買い物の合計額がじわじわと増えています。その結果、日常的な出費が家計を圧迫し、住宅ローン返済にまわせる金額が限られてしまうという家庭も多くなっています。
電気代・ガス代はエネルギー価格の高騰、再エネ賦課金の増加、基本料金の見直しなどが重なって値上がりしています。特にオール電化住宅や日中在宅時間の長いご家庭では、光熱費の使用量が多くなる傾向があるため、設計段階から光熱費を抑える工夫を欠かさないようにしなくてはいけません。
医療保険や火災保険の保険料は高水準で推移しており、多くの家庭で生活費の一部として定着しています。教育費も学用品代や塾代などで支出が増えやすい傾向があります。また、スマホやインターネットなどの通信費も各家庭で複数契約が当たり前となっており、家計への影響が無視できなくなっています。
このように住宅ローン“以外”にも支出が増えている現代では「建てたあとの暮らしも見据えた設計と資金計画」がますます重要となっています。
それでは、現在の情勢の中で家を建てる際、どのような点に注意すればよいのでしょうか?以下の7つのポイントを意識していきましょう。
必要以上に豪華な設備や最新機能にこだわりすぎず、生活に本当に必要な仕様を見極めて導入することが大切です。たとえば、高級グレードのキッチンや浴室、過度に多機能な家電などは、見栄えは良くても使用頻度が少ない場合も多く、費用対効果が低くなることがあります。実際の暮らしをシミュレーションしながら「これなら標準仕様で十分」と判断できる部分は思い切って引き算し、必要なところだけに予算を集中させる。この“引き算の設計”こそが、賢い家づくりの基本です。省く勇気が将来の家計の安心につながります。
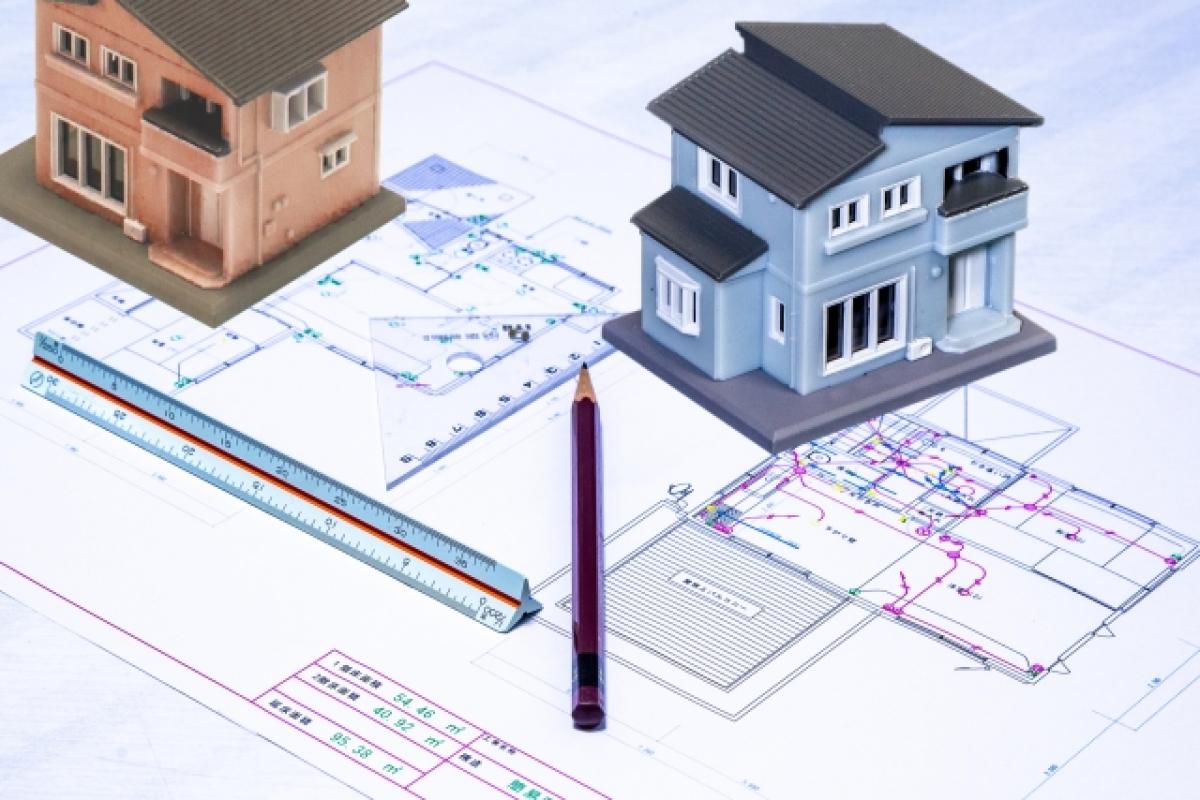
家の大きさは広ければ良いというわけではありません。家族の人数やライフスタイルに見合った広さでなければ空間が余ってしまい、無駄な建築費や冷暖房コスト、掃除の手間が発生することになります。生活動線がスムーズで家事効率の良い間取りを意識することで、実際の暮らしにフィットした住まいになります。設計段階では「実際にどの空間を日常的に使うのか」「どこまでが本当に必要か」を明確にすることが無理のない間取りづくりの第一歩です。

断熱性能を高めることで冬場の暖房効率が上がり、夏場も外気の熱を遮ることができるため冷暖房費の削減につながります。また、効率の良い換気設備を選ぶことで外気の影響を最小限に抑えながら室内の空気を快適に保てるため、エアコンの使用頻度を減らす効果も期待できます。さらに、太陽光発電の導入を検討することで自家発電によって電気代を削減できます。これらの工夫は初期費用こそ必要ですが、長期的には確かな節約と快適な住環境の維持につながります。ただし、太陽光発電の採用には設置コストやライフスタイルに応じた電力使用量などを踏まえてしっかりとシミュレーションを行い、経済的メリットが確実に見込める場合に導入するのが良いでしょう。

国や自治体が用意する補助金・優遇税制を調べて、活用できるものはすべて使いましょう。たとえば、子育て世帯や若者夫婦世帯を対象とした住宅取得支援や長期優良住宅・ZEH住宅といった省エネ住宅への補助金制度、固定資産税の軽減措置、さらには住宅ローン控除などがあります。特に省エネ性能の高い住宅に対しては優遇措置が手厚く、設計段階でこれらの条件を意識することで、結果的にトータルコストを抑えることにもつながります。
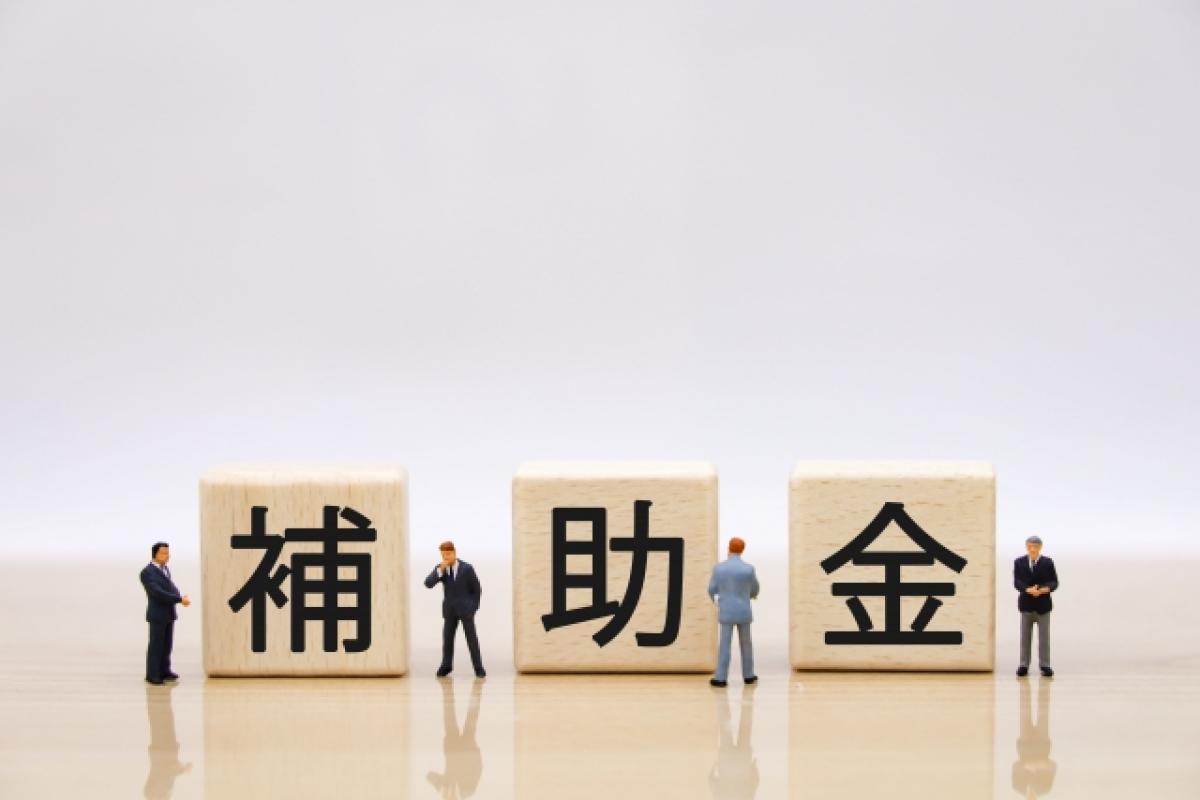
可変性のある間取りや将来的なバリアフリー対応を想定することで、将来の改修費用を抑えることができます。たとえば、子どもが成長した後に仕切りを外して1部屋にできる構造や将来的に手すりやスロープを設置しやすいよう壁面を補強しておくなど、ライフステージの変化に対応できる設計が効果的です。また、高齢になったときに階段の上り下りが負担にならないよう、1階に寝室を設けるなどの工夫も将来のリフォーム費用を抑える大きなポイントになります。

エアコンの全室設置や外構工事、カーポートの設置や庭の整備など、すぐに必要でない支出は入居後の暮らしを通じて優先順位を見極めながら、タイミングを見て実施していくのも賢い方法です。必要かどうかを実際の生活で判断してから導入することで無駄な出費を抑え、家計への負担を軽減できます。

資金計画から設計、施工までをトータルで支援してくれる住宅会社を選ぶことで予算に応じた最適な提案を受けられ、ムダのない家づくりが実現しやすくなります。自分たちの暮らしに合った間取りや設備を提案してくれる、信頼できるパートナーに出会うためには丁寧な情報収集としっかりとした相談の時間を確保することが欠かせません。
また、不動産会社では建物そのものの構造や仕様、実際の住み心地についてまで詳しく説明できないことも多く、建物に関する深い相談をしたい場合は、最初から住宅会社に相談するのがおすすめです。経験豊富で信頼できる担当者を見つけることが、満足のいく家づくりの第一歩となります。

建築費も生活費も上昇している今、それでも「家が欲しい」と思う気持ちは大切にしたいですよね。ただし、焦って決断をしてしまうと将来の暮らしに無理が出てしまう可能性もあります。
今こそ必要なのは、“自分たちにとって何が必要で、何が不要か”を見極める目。そして、将来の生活も見据えたバランスの良い資金計画と家づくりです。
家は「高い時期だから諦める」のではなく「工夫次第で可能性が広がる」選択肢として捉えることが今の時代には求められています。

私たちぽんたのいえは、「ただ家が売れればいい」とは思っていません。
創業は 1958 年、半世紀を超えて地元東三河の公共事業を担ってきました。
私たちがみなさまと共に作り上げてきた街。
住まわれている⽅が笑顔になるよう想いを乗せてお仕事をしてきました。
今ぽんたのいえで、⼾建のお家を建てているその理由も同じです。
『みなさまに笑顔で暮らしていただくため』
笑顔で暮らす、これほど素敵な毎⽇はありません。
⼀緒に夢の家づくりを始めましょう。
ぽんたのいえ3つのポイント
①ローコスト住宅なのに新築⾃由設計
②ローコストなのに安⼼で安全な適正施⼯期間
③建てた後の安⼼なアフターメンテナンス対応
ご相談お待ちしております。
ご連絡先
フリーダイヤル 0120-56-3948 (受付時間: 10:00~18:00)
お問い合わせフォーム
https://ponta-house.net/contact.php