
地球温暖化や気候変動の影響で全国各地で台風や豪雨による被害が年々深刻化しています。愛知県東三河エリアも例外ではなく、過去には台風による冠水被害や暴風による家屋破損が相次いだ地域です。
そんな時代だからこそ、家づくりにおいて「収納」「採光」「動線」だけでなく、「災害への備え」も重要視されるようになってきました。
この記事では、異常気象に対応するための住宅設計の工夫について、特に台風・豪雨に焦点を当て、地域性を踏まえた具体的なアイデアをご紹介します。
Contents
近年の気象庁データによると日本の年間降水量は増加傾向にあり、局地的な集中豪雨も頻発しています。特に東三河地域では、豊川水系の氾濫リスクや台風による強風・飛来物の被害が懸念されており、「通常の家」では防げない被害が現実のものとなっています。
こうした背景から家を建てる際には、ただ「快適」なだけでなく、「守ってくれる家」という視点が求められる時代になりました。では、どんな設計がそれを可能にするのでしょうか?

住宅の外観や屋根は台風や豪雨といった自然災害に対して最前線で立ち向かう存在です。特に日本の気候では風雨による建物へのダメージが蓄積されやすく、日々のメンテナンスだけでなくそもそもの設計段階から災害対策を講じることが求められています。
ここでは軒の出し方、屋根材の選び方、そして雨仕切りや玄関・勝手口の浸水対策といった家の「顔」となる部分に着目し、風雨に強い家づくりの具体的な工夫をご紹介します。
軒や庇が深く設計されている家は、台風や強い横殴りの雨でも窓からの浸水を防ぐ効果があります。特にリビングなど大きな掃き出し窓のある場所では、軒の出を60cm以上確保することで雨が室内に吹き込むリスクを大幅に軽減できます。
また、夏場の強い日差しを遮る役割も果たすため、省エネ効果にもつながります。深い軒は見た目にも重厚感があり、デザイン性の向上にも貢献します。
なお、軒を深く設けるためには屋根構造の調整や部材の増加が必要になることから、一般的な設計と比べてやや建築コストが上がる場合があります。それでも、台風や強い日差しへの対応力を高める効果を考えれば、長い目で見て大きな安心につながる設計と言えるでしょう。
予算に少し余裕をもたせてでも、積極的に取り入れたい工夫の一つといえるでしょう。

屋根は家の中で最も風の影響を受けやすい部分です。例えば、台風の際に瓦が飛ばされたという被害は毎年のように報告されています。
耐風性能の高いガルバリウム鋼板やしっかりと固定された軽量瓦など、地域の気候に合った屋根材を選ぶことが重要です。
また、屋根の形状にも注目しましょう。切妻屋根や寄棟屋根は風の流れを受け流しやすく、台風の多い地域では特に適した形状です。

玄関や勝手口は低い位置に設置されていることが多いため、浸水リスクが高まります。そのため、以下のような工夫が有効です。
・玄関ポーチに段差を設けることで雨水が直接玄関に流れ込むのを防ぐ
・ドアまわりに防水パッキンや水返しを設けて吹き込みや浸水をブロック
・勝手口にはステップ付きのスロープや雨水を逃がす排水口を設ける
これらの対策を組み合わせることで、万が一の浸水リスクを最小限に抑えることができます。
また、実際に家を建てる前に地域の方々の体験談や事例を参考にすることも大切です。
過去の浸水状況や被害の履歴を自治体の公開情報や近隣の声から確認しておくことで、自分たちの住まいにどのような備えが必要か、具体的なイメージを持つことができます。

建物本体の耐水性をどれだけ高めても、敷地全体の水はけが悪ければ浸水のリスクは消えません。特に東三河エリアのように大雨や集中豪雨の可能性が高い地域では、土地の高さ、勾配、排水設備の整備など、敷地全体の視点で水害対策を講じることが重要です。
ここでは、雨水の流れを適切にコントロールし、家そのものと暮らしを守るための敷地設計や排水に関する工夫について解説します。

家本体の設計と同じくらい重要なのが敷地の高さや形状です。近年では、「盛土」をして周囲の土地よりも若干高くするケースが増えています。これにより、大雨時でも水が敷地内に滞留しにくくなります。
また、地面の傾斜を適切に設けることで雨水が建物に向かって流れ込むのを防ぎます。水はけの悪い土地では暗渠排水(あんきょはいすい)を設置することで、地中の排水処理も強化可能です。
暗渠排水とは、地面の下に設置された排水管や砂利層を通じて、地中の水を効率よく排出する仕組みです。ここでいう「砂利層」とは、排水管の周囲に敷き詰めた小石の層を指し、水を通しやすい性質を活かして周辺の水分をスムーズに集め排水管へと導く役割を果たします。
表面には見えないため景観を損なわず、ぬかるみや地下水の滞留による建物への影響を抑える効果があります。
雨樋だけでは処理しきれない集中豪雨では敷地内の排水能力が問われます。そのため、
・排水マスの数を増やし、分散配置することで急激な雨量にも対応
・雨樋の口径を太めに設定し、排水速度を上げる
・地面との勾配をしっかり設け、排水溝へ自然に流れる設計を
これらにより、水の逃げ道を確保し、建物や基礎へのダメージを防ぐことができます。
なお、こうした排水計画は住宅会社によって対応の差が大きいため、事前に「集中豪雨への対策はどうしていますか?」と確認することが大切です。外構や造成を一括で請け負っている会社や地域の水害情報に詳しい工務店では、排水マスの分散配置や勾配設計などの工夫にも積極的に取り組んでくれるでしょう。
雨水が地表にたまりやすい庭や駐車場では、透水性の高い舗装を使うことで浸水対策になります。具体的には、
・砕石と防草シートを組み合わせた「簡易透水ゾーン」の設置
・インターロッキングなど隙間のある舗装材を活用
・花壇や芝生ゾーンを効果的に配置し、土の吸水力を活用
見た目にもナチュラルでおしゃれに仕上がり、機能性も兼ね備えた外構になります。
透水性舗装を採用することで雨水がその場で地中に浸透しやすくなり、水たまりやぬかるみの発生を防ぐことができます。特に駐車場など広い面積に水が滞留しやすい場所では見た目のデザイン性だけでなく、日常の使い勝手や安全性の向上にもつながります。
また、雨水を適切に処理することで基礎への影響や建物周辺の土壌流出を防ぎ、長期的な住まいの保全にも貢献します。
愛知県東三河地域には地形や気候に応じた災害リスクがいくつか存在します。どのようなリスクがあるのか、具体的に見ていきましょう。
河川の氾濫による床上・床下浸水のリスクを把握するためには自治体が公表しているハザードマップを確認するようにしましょう。ハザードマップでは想定される浸水の深さや範囲、避難経路などが視覚的に示されており、土地選びや設計計画の判断材料として非常に有効です。
特に、過去に浸水履歴がある地域や地盤が低く水が溜まりやすい場所では、基礎の高さを確保する設計や敷地のかさ上げを行うことで建物内部への浸水リスクを大幅に軽減できます。また、周囲の道路や隣地との高低差も考慮しながら、排水の方向や水の逃げ道を整えておくことが、万が一の事態に備える重要な対策となります。
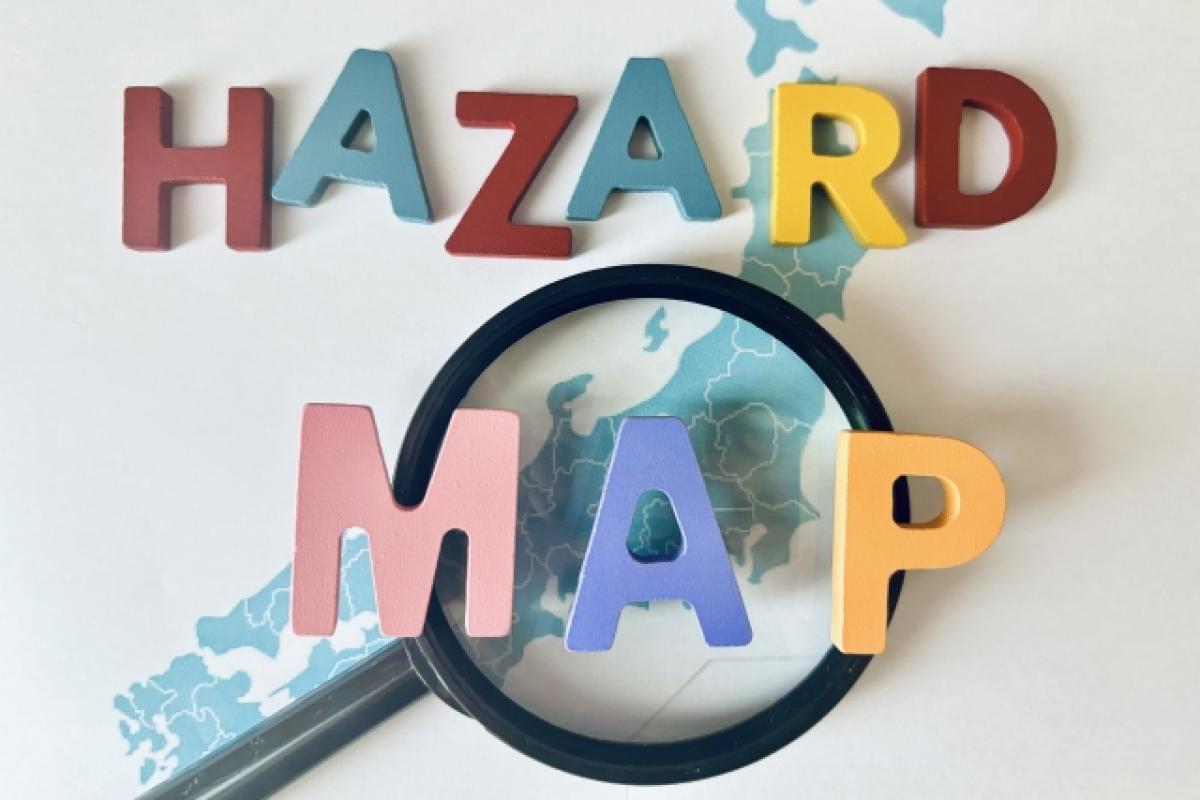
海沿いの地域では風速が強まるだけでなく、海風に含まれる塩分が建材の腐食を早める原因になることもあります。特に台風の際には潮風が風雨とともに強く吹き付け、金属部材や外壁材、サッシ周辺に塩分が付着しやすくなります。
このような地域で住宅を建てる場合は、屋根や外壁には塩害に強いガルバリウム鋼板やフッ素塗装仕上げの外装材などを採用することがおすすめです。また、雨どいや換気フード、ビスなどの金属部材には防錆加工やステンレス製の部材を選ぶことで、長期間にわたる耐久性を確保できます。
定期的な洗浄やメンテナンスも塩害対策には有効です。とくに台風通過後などは、外壁や金属部品に付着した塩分を水で洗い流すだけでも劣化の進行を抑える効果があります。

ガルバリウム鋼板はアルミ55%・亜鉛43.5%・シリコン1%の合金で構成されており、一般的な鉄製品よりも高い耐食性を持ちます。一定の耐塩害性能があり、多くの住宅で採用されていますが、海岸線からおおむね500m以内の強塩害地域では劣化の進行が早まる可能性があるため注意が必要です。
そのような環境では、さらに塩害に強い「フッ素塗装仕上げの外壁材」や「純アルミ系の板金」、また「樹脂系サイディング」「窯業系サイディング」なども選択肢となります。
サイディング材は金属腐食の心配が少なく、デザインや色の選択肢が豊富で意匠性と機能性を両立した外装材として人気があります。

内陸部は一見安全そうに見えますが急傾斜の地形が多いため、短時間に大量の雨が降ると土砂とともに一気に水が流れ込むことがあります。このような地域では、敷地の上流から流れ込む水や土砂を建物周辺に入れないための対策が不可欠です。
具体的には、敷地の上部に集水桝や排水溝を設けて雨水の流れをコントロールしたり、法面(のりめん)部分にコンクリート擁壁や植生マットを施工して土砂流出を抑制することが有効です。また、建物の背面や斜面に面した側には雨水をうまく受け流すための「水切り溝」や「透水性砕石」を敷設し、過剰な水圧や湿気の滞留を防ぎましょう。
排水計画や土留め工事は、設計段階から周囲の地形と連動して検討することで災害リスクを大きく軽減できます。

高台では建物への風圧や飛来物対策が必要になり、低地では逆に排水のしやすさが課題になります。土地の標高や周囲の地形、過去の災害履歴を総合的にチェックし、適切な設計を検討することが重要です。
家の設計だけでなく、「その土地に建てて大丈夫か」を見極める視点も欠かせません。
例えば、同じ市内であっても、台地・扇状地・低地といった地形によってリスクは大きく異なります。造成されたばかりの新興住宅地では、見た目ではわからない排水経路の不備や過去の浸水実績がある場所もあります。
そのため、購入前には自治体が提供する地形図やハザードマップ、地歴情報(昔は田んぼや沼地だったかどうか)を確認することが重要です。また、不動産会社や住宅会社の担当者に「過去に災害の履歴はあるか」「近隣で雨水があふれたことはあるか」などを質問してみるのもよいでしょう。
こうした事前の確認を怠らず、土地の性質を十分に理解したうえで設計を進めることが、災害に強い家づくりへの第一歩となります。

異常気象はもはや特別な出来事ではなく、「毎年起こる現象」として捉えるべき時代に突入しています。建ててから後悔しないためにも、軒の深さ、屋根材、排水計画、土地の傾斜など、住宅のあらゆる部分に“耐災害設計”の視点を持ち込みましょう。
家族が安心して暮らし続けられる家を実現するためにこうした工夫を取り入れてみてはいかがでしょうか。

私たちぽんたのいえは、「ただ家が売れればいい」とは思っていません。
創業は 1958 年、半世紀を超えて地元東三河の公共事業を担ってきました。
私たちがみなさまと共に作り上げてきた街。
住まわれている⽅が笑顔になるよう想いを乗せてお仕事をしてきました。
今ぽんたのいえで、⼾建のお家を建てているその理由も同じです。
『みなさまに笑顔で暮らしていただくため』
笑顔で暮らす、これほど素敵な毎⽇はありません。
⼀緒に夢の家づくりを始めましょう。
ぽんたのいえ3つのポイント
①ローコスト住宅なのに新築⾃由設計
②ローコストなのに安⼼で安全な適正施⼯期間
③建てた後の安⼼なアフターメンテナンス対応
ご相談お待ちしております。
ご連絡先
フリーダイヤル 0120-56-3948 (受付時間: 10:00~18:00)
お問い合わせフォーム
https://ponta-house.net/contact.php
