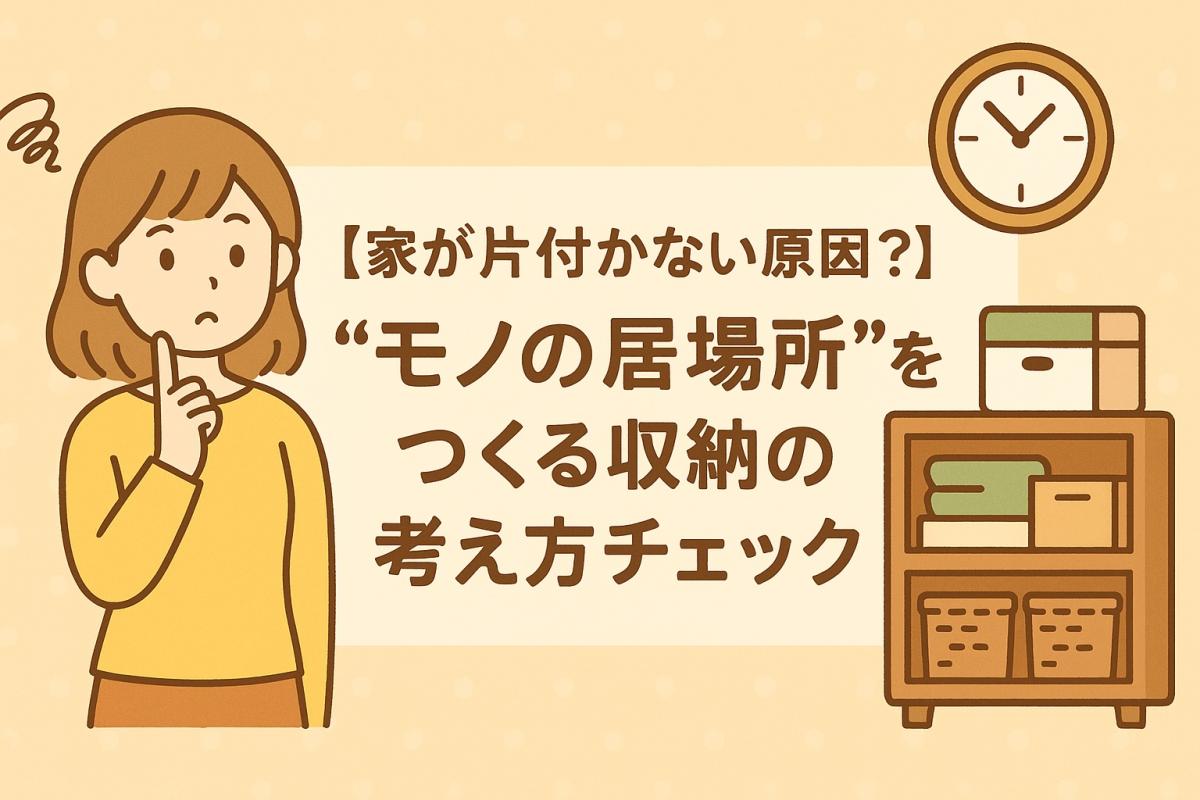
新築の家に引っ越したのになんだかすぐ散らかる。
「収納はたくさんあるのに片付かない」
「片付けてもすぐ元に戻る」と感じるご家庭も多く見受けられます。
実は、“モノの量”ではなく、“モノの居場所が決まっていない”ことが散らかりやすさの原因になっているケースが多いのです。収納の数や広さだけで満足してしまうと、生活の中で「どこにしまう?」「誰が戻す?」と迷う場面が増えてしまい、結果として片付かない家になってしまいます。
この記事では、新築で“片付く暮らし”を実現するために知っておきたい収納の考え方を紹介します。 使う場所・動線・家族のクセをふまえた収納設計のヒントをぜひ家づくりや暮らしの見直しに役立ててみてください。
モノが片付かないと感じる家では、「しまう場所が決まっていない」という共通点があります。収納が足りないわけではなく、モノにとっての“定位置”がないことで家族が迷って出しっぱなしになってしまうのです。
ここでは、片付く家に共通する「モノの居場所づくり」のポイントをチェックリスト形式でご紹介します。
日用品(文具・タオル・掃除道具など)は、実際に使う場所のすぐそばに収納スペースがあるかどうかが暮らしやすさを大きく左右します。たとえば、掃除道具がリビングから遠くにあると、「あとでいいや」と出しっぱなしにしてしまうことになる可能性があります。
「使ったらすぐ戻す」が自然にできるようにするには、収納を“動作の流れ”の中に組み込むことがポイントです。必要な場所に必要な収納を用意するだけで片付けの手間がぐっと減ります。

子どものおもちゃやランドセル、洗濯物などは「自分で戻せる高さ」にあるかどうかがとても重要です。たとえば、ランドセルが大人の目線に合わせた棚にあると、子どもは毎日の片付けに手間を感じてしまいます。
また、洗濯物をしまう場所が屈まないと届かない場所だったり、逆に高すぎたりすると家族が自分で片付ける習慣が定着しにくくなります。
「使う人の身長・動作・習慣」に合わせて収納の高さや位置を調整することが自然と片付く環境をつくるための大きなポイントになります。

書類・小物・ストック用品などは、引き出しやボックスにラベリングすることで誰でも一目でわかるようになり、管理や片付けが格段にスムーズになります。特に家族が複数いる家庭では、「これはどこに戻すの?」という迷いが積み重なることで散らかりやすくなる傾向があります。
たとえば、食品ストックのケースに「缶詰」「乾物」「お菓子」などとラベルを貼るだけで子どもでもすぐに戻せるようになりますし、日用品の収納棚も「洗剤」「ストック用」などの表示をしておけば、家族全員が自然と片付けに参加できるようになります。
ラベリングは手間がかかるように見えて、家事の時短とストレス軽減につながる小さな工夫です。

コップやタオル、食器などの生活用品は、日常的に使うものと来客用とで役割が異なります。これらが一緒になっていると、「普段使いのつもりで出したら来客用だった」といった無駄な動線やストレスが生まれてしまいます。
普段使いのアイテムは取り出しやすい位置に配置し、来客用のものは奥の棚や吊り戸棚など、使用頻度の低いスペースにしまっておくのが基本です。また、見た目が似ている食器などは、ラベリングや使用シーンごとに分類することで迷わず出し入れができるようになります。
日常と来客の使い分けが明確になると収納の流れが自然に整い、結果として“散らかりにくい仕組み”ができあがります。

収納が多ければ多いほど家が片付くと思っていませんか? しかし実際は、「どこにあるか」「どう使うか」のほうがはるかに大切なことなのです。たとえ大容量の収納があっても日々の動線から外れていたり、使いにくい高さにあったりすると結局モノは出しっぱなしになってしまうことが多くあります。
ここでは、収納の「量」ではなく「配置と使いやすさ」に注目した家づくりのポイントをご紹介します。
たとえば「玄関→脱衣所→洗濯機→クローゼット」のように生活の一連の動きに合わせて収納が配置されていると、自然と片付けがしやすくなります。 動作に沿った収納計画は、“つい出しっぱなし”を防ぎ、動線をスムーズに保つ大きな要素になります。
毎日の行動パターンを思い描きながら、無理なく使える収納の位置を検討することが大切です。

収納の扉を開けるのが少し面倒に感じてつい出しっぱなしになってしまうことも少なくありません。 日常的によく使うものはオープン棚などの「見せる収納」を活用し、来客時やあまり使わないものは「隠す収納」にすると、片付けの負担を減らしながら空間もすっきり保てます。
使いやすさを意識した収納の使い分けが、自然と整った暮らしをサポートしてくれます。

片付いているお家の多くには、「家族全員が迷わず行動できる仕組み」があります。特別な整理整頓術を身につけたわけではなく、日常の中で“モノの居場所”や“収納ルール”が自然に共有されているのが特徴です。
ここでは、そんな「使いこなせる収納」のヒントとなる共通点をご紹介します。

「ここに戻す」というルールが家族の中で自然と共有されていることが家の中をスッキリ保つポイントになります。
誰か一人だけが場所を把握しているのではなく、家族みんなが使ったものを元の場所に戻せる環境づくりが片付けのストレスを減らします。
朝の準備がしやすいように設けた「身支度コーナー」や帰宅後にランドセルや教科書をすぐ片付けられる「専用の置き場」など、日々の動線や家族の行動パターンを反映した収納があると自然とモノが整い、暮らしのリズムもスムーズになります。
片付く家には、共通して「モノの居場所が決まっている」という特徴があります。 収納の広さや数だけに注目するのではなく、「誰が」「いつ」「どうやって」しまうのかを想定して設計・整理していくことが大切です。
家づくりのタイミングで収納の考え方を見直すことで暮らしやすさがぐっと変わります。 ぜひチェックリストを参考に、“モノの迷子”がいなくなる家づくりを目指してみてください。

私たちぽんたのいえは、「ただ家が売れればいい」とは思っていません。
創業は 1958 年、半世紀を超えて地元東三河の公共事業を担ってきました。
私たちがみなさまと共に作り上げてきた街。
住まわれている⽅が笑顔になるよう想いを乗せてお仕事をしてきました。
今ぽんたのいえで、⼾建のお家を建てているその理由も同じです。
『みなさまに笑顔で暮らしていただくため』
笑顔で暮らす、これほど素敵な毎⽇はありません。
⼀緒に夢の家づくりを始めましょう。
ぽんたのいえ3つのポイント
①ローコスト住宅なのに新築⾃由設計
②ローコストなのに安⼼で安全な適正施⼯期間
③建てた後の安⼼なアフターメンテナンス対応
ご相談お待ちしております。
ご連絡先
フリーダイヤル 0120-56-3948 (受付時間: 10:00~18:00)
お問い合わせフォーム
https://ponta-house.net/contact.php
