
近年、建築費や人件費、資材価格の上昇が続く中、住宅ローン金利のニュースも増え、「今は待つべきか、それとも建てるべきか」と悩む家庭が多いのではないでしょうか。特に2025年時点では、短期の指標と連動しやすい変動金利は歴史的に見て低い水準にとどまり、長期の指標に影響されやすい固定金利は上げ下げを繰り返しながらも落ち着いた動きが見られる場面があります。
一方で、東三河の賃貸の家賃は緩やかに上昇が続き、毎月の住居費を圧迫しています。それだけでなく今後に起こりうる可能性のある、家族構成の変化や転勤の可能性、教育費や車の買い替え、老後資金といったライフプランも重なるため、判断は簡単にはできません。
この記事では金利の“今”をふまえたうえで、月々の返済や手元にある資金、将来の維持管理費といった実生活に直結する視点から、「今建てるべき人」と「少し待つほうがよい人」を整理していきます。
数字の損得だけではなく、住み心地や毎日の安心感まで含めて検討できるように、チェックポイントや具体的な手順も丁寧にまとめました。結論から言えば、家賃上昇と金利リスクを見渡すと“今のうちに計画を固める価値は高い”ケースが多いのですが、だからと言って焦って契約するのではなく、返済や貯蓄を確認し、将来の出費も踏まえた上で段階的に判断していくことが後悔のない家づくりにつながります。
Contents
金利は住宅ローンの総額や毎月の返済額に直結します。そのため、まずは「現在」の特徴を整理しておきましょう。
ここでは“変動”と“固定”の傾向を分けて見ていきます。
住宅ローンの金利は、国内の金融政策や長期金利の動き、世界経済のニュースなどの影響を受けますが、暮らしの判断に落とし込むには、数値だけでなく“家計への影響の出方”を理解することがポイントになります。
変動金利は短期の金利情勢に連動しやすく、ここ数年は歴史的に見て低い水準が続いています。金融機関によって優遇幅は異なるものの、条件が合えば低い金利を提示されることが多く、月々の支払いを比較的抑えることができるところが特徴です。
その一方、将来の金利上昇局面では返済額が増える可能性があるため、後述する「返済比率」に余裕を持たせることや繰上返済の計画を事前に用意しておく必要があります。

固定金利(全期間固定や長期固定)は、長期金利の影響を受けやすく、国内外の経済ニュースによって上下する場面があります。
直近では上昇と調整を繰り返しながらも、足元では横ばい〜やや落ち着いた水準にあります。変動に比べて初期の金利は高くなりますが、全期間固定の場合は、返済額が契約時に確定するという安心感があり、将来的なことも含めて家計管理がしやすいのがメリットの一つです。

金利は小数点以下の小さな差であっても、35年といった長い期間で算出しますと大きな金額の差が出てしまういます。
月々の家計バランスを守るために次の2点を押さえておきましょう。
同じ借入額・同じ期間であっても、金利が少し違うだけで総返済額の差は大きくなります。シミュレーションでは、仮に3,500万円の借入をして金利が0.5%変わると、総額で350万円以上の差が出ます。
タイミングを逃す、あるいは将来の金利上昇のことを考えずに借りてしまうと、その差は家計に圧しかかってきます。重要なのは、契約前に複数の金利パターンを比べ、返済比率に余裕を持たせることです。

近年は賃貸の家賃もじわじわと上がってきています。
家賃が上がり続けると、住居費が固定されないという不安が残ります。しかし、新築を購入し、住宅ローンに切り替えることで固定金利なら返済額、変動でも当面の返済額をある程度“見える化”することができます。
ライフプラン上、長くその地域に住む予定がある家庭ほど、支出をコントロールしやすい方法という選択肢に繋がります。

「いま建てるか、待つか」は家庭の状況によって答えが変わってきます。
金利や家賃の動きに加えて、ライフイベントや手元資金、毎月の家計の余力を合わせて見てみましょう。

・現在の家賃が高く、住宅ローン返済と大きく変わらない、あるいはローン返済の方が下がる見込みがある
・家族構成や勤務地が当面変わらない見通しで、居住エリアを固定化できる
・頭金や諸費用をまかなえる貯蓄があり、緊急資金(生活費6〜12か月分)も確保できる
・金利上昇局面に備え、返済比率に余裕を持たせる設計ができる
これらのいずれかに当てはまる家庭は、新築を購入したことによる住居費の固定化や家賃上昇の回避といったメリットが得られやすくなります。変動金利の低さを生かしつつ、将来の上昇に備えた“余力のある返済計画”を組む、もしくは固定金利で返済額を確定させる、といった選択が現実的です。
・転職・転勤・独立の予定が近く、収入や居住地が変わる可能性が高い
・頭金や諸費用を十分に用意できず、手元資金が少なくなる
・建築費の動向や物件選びについて、比較検討がまだ十分にできていない
この場合は、情報収集と貯蓄の強化を優先しましょう。焦って契約するよりも、選択肢を増やす期間に充てた方が良く、さらに並行して、家賃の見直しや一時的な住み替えで住居費を抑える工夫も検討すると頭金づくりが進みます。ただし、必ずしも頭金を用意しなければならないわけではなく、頭金ゼロでも無理のない返済計画を立てられるのであればあまり注視しなくても問題ありません。
大切なことは、借入額と返済比率を適切に設定し、家計に負担をかけない資金計画を組むことです。
意思決定の軸が増えるほど迷いも増えてしまいます。
ここでは、迷ったときに立ち返れる“3つの視点”を具体的な手順に落とし込みますので順番に確認していきましょう。
住宅ローンによって借入をするか否かを判断する際に、金利の高低に注視してしまうことが多いのですが、実は、家計の健全性を保つ上で最優先すべきは返済比率(年収に占める年間返済額の割合)なのです。目安としては28%以内におさめると良いでしょう。
将来の変動に備え、金利が1%上がった場合でも問題なく返済できるのかを試算し、毎月の余力が残るラインを見極めておきましょう。
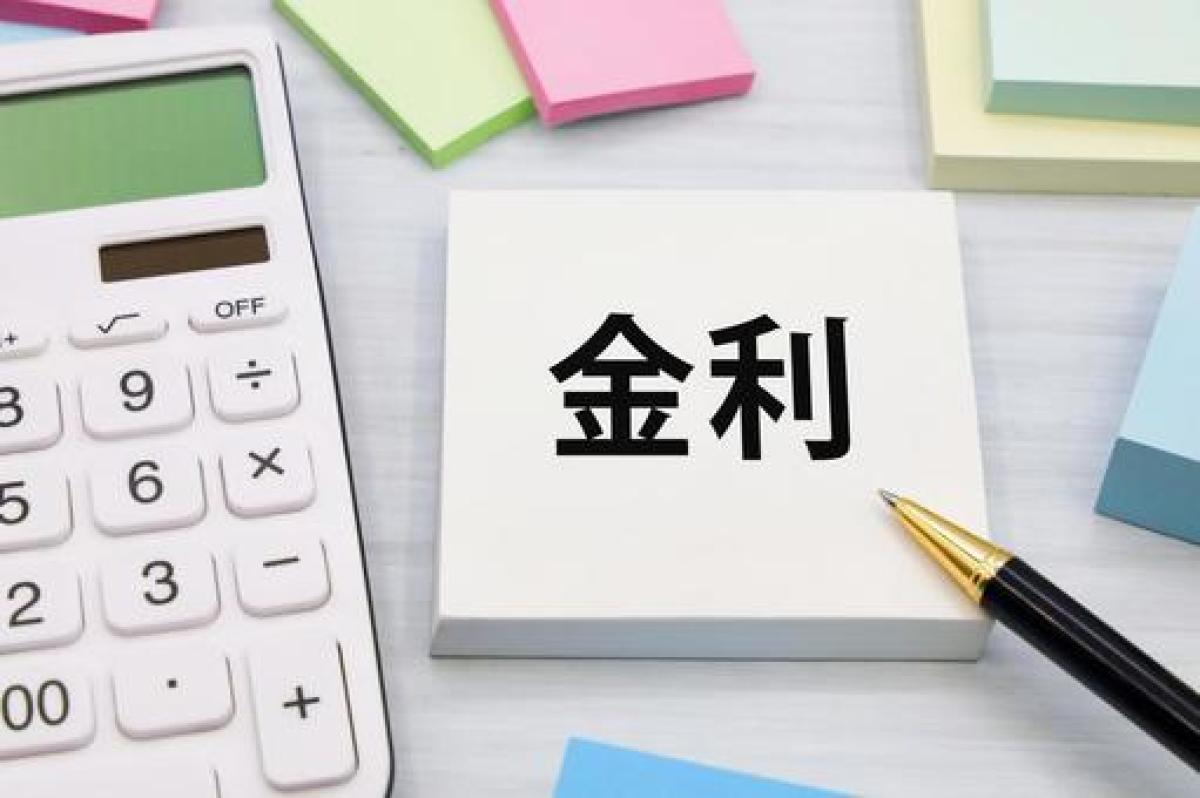
ボーナスは景気や会社業績の影響を受けるため、数年先のボーナスを正確に見通すことはできません。ボーナス返済を組み込んでしまうと、思わぬ減額時に家計が苦しくなってしまいます。
毎月の給与だけで返せる範囲に設定し、余裕がある年は繰上返済や貯蓄に回す計画が良いでしょう。

住宅は建てて終わりではありません。外壁や屋根、水回り設備など、10〜20年スパンで交換・更新の費用が必要になります。
資金計画に“将来のメンテナンス費”の項目を用意しておくことで、金利に左右されず、長期的な心の安定を生むことでしょう。
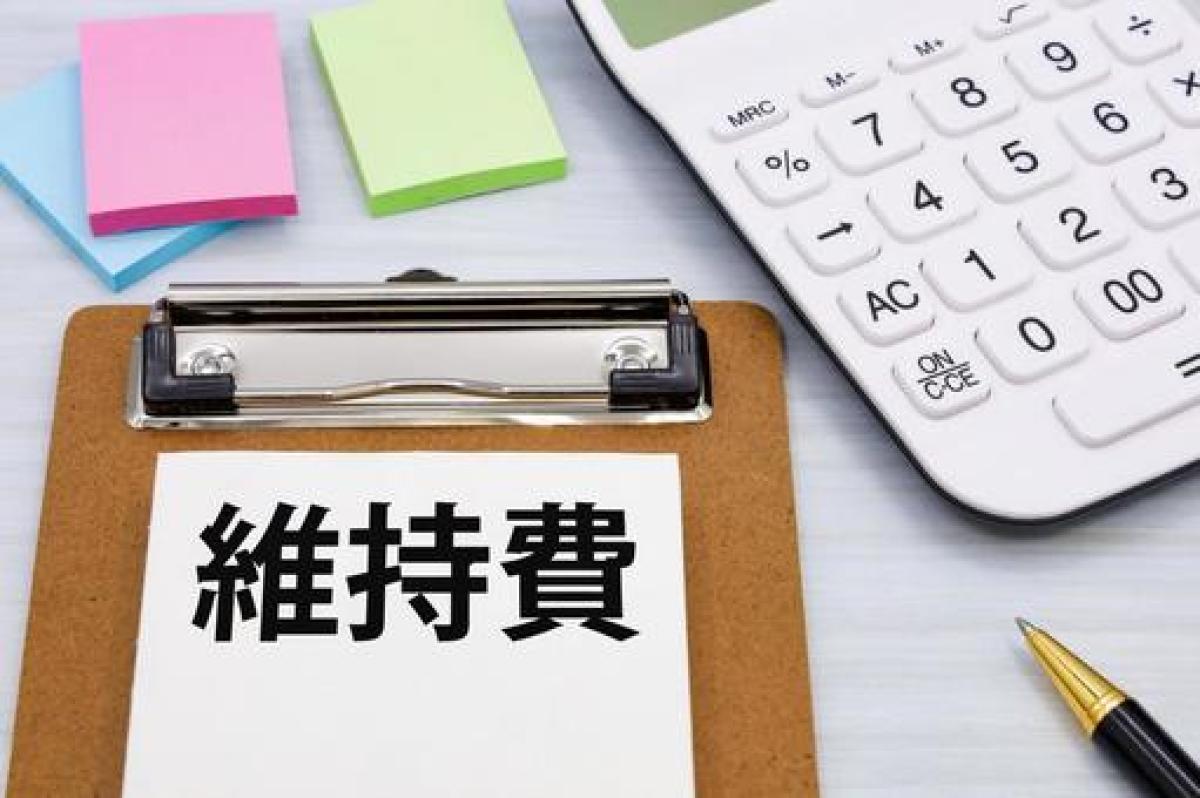
それぞれの家庭によって、「今建てるか、もう少し待つか」の答えは異なります。ただ、これからお伝えする環境の変化を踏まえると、“今のうちに計画を具体的に進める”ことがより良い選択肢となるでしょう。
ここからは、実際の暮らしに照らし合わせて、押さえておきたいポイントをお伝えします。

仮に現在お住まいの集合住宅や借家にて住居費を毎年見直すような傾向がある環境では、家賃を住宅ローンに切り替えて返済額を見える化するとメリットが増すことでしょう。
固定金利なら返済額を固定でき、変動を選ぶ場合も返済比率に余裕を持たせることで、万が一の上昇局面でも慌てずに対応できるでしょう。
資材価格の上昇で、建築費は中長期的に見ると高止まりの傾向があります。その一方で、プランの工夫や仕様の選択で総額を抑えることは十分に可能です。
例えば、
「延床面積をコンパクトに」
「水回りを近接させて配管コストを抑える」
「既製サイズを賢く選ぶ」など、設計段階での工夫によって建築費は大きく変化します。新築の購入は金利だけでなく、“建て方”で支出を整えることができるのです。
今のうちに返済比率に余裕を持たせた状態で借入後の家計に“ゆとり”を持たせておけば、将来の金利変動に対応できるようになります。
変動を選ぶ場合は、返済額が上がる可能性を前提に家計の余力を残し、固定を選ぶ場合は当面の見通しが立てやすくなります。
どちらにしても、「上がるかもしれない」に対しての行動で備えることが大切です。
家賃が上がるたびに引越しや住み替えを検討するのは、大きな時間と労力がかかります。今のうちに住まいを決めることで通学や通勤の動線、地域の人間関係、災害時の避難先など、生活の基盤が安定させましょう。
金額だけの損得でなく、毎日の安心感や時間の価値も判断材料に入れてみてください。
ここからは、実際に「今建てる」前提で、無理のない進め方を7ステップでまとめます。各ステップが次のステップにつながるよう流れを作っていますので、是非参考にしてください。

まずは手取り収入から、食費・通信・保険・車関連などの固定費を洗い出していきます。
現状の住居費(家賃・駐車場代・更新料など)も含め、毎月、“確実に出ていくお金”を把握しましょう。
ここで浮いた固定費は、そのまま将来の繰上返済やメンテナンス費の積立に回す計画をします。
家計の棚卸しをした上で、返済比率の上限を28%以内に設定します。将来必要になる教育費や車の買い替え、旅行などの“暮らしの楽しみ”への支出に圧迫させない水準にすることがポイントです。
”ここを超えない借入額にする”というルールを先に決めると、返済による後悔を大きく減らすことができます。
「現状の金利」「+0.5%」「+1.0%」の3パターンを用意し、月々返済・総返済額・返済比率がどう変わるかを比較します。変動を選ぶ場合でも、この“上振れ”をあらかじめ家計に組み込んでおけば、将来的な見直しの判断が冷静にできます。
シミュレーションは多くの金融機関のホームページにて無料で試算することができます。
ボーナス併用は避け、毎月の返済だけで完結できる計画にしましょう。仮に余裕が出た分は、繰上返済用の口座やメンテナンス費用の積立に充てると良いでしょう。
返済額を増やすより、“貯めてから減らす”方が柔軟に対応できますし、心の余裕も生まれます。
同じ性能でも間取りや設備の工夫で建築費や入居後の電気代が変わります。延床面積を少しコンパクトにする、設備を標準の範囲で選ぶ、水回りを1ヶ所にまとめるなど、設計段階でできる改善はたくさんあります。
コストの“総量”を整えることで、金利の上げ下げに対する耐性が増していきます。
外壁塗装、屋根の点検、給湯器や水回り設備の交換など、10〜20年単位で必要になる出費を一覧化し、年額に直して積み立てていきます。これにより、ローン返済と維持費の二重負担が重なる時期でも、家計に過度な負担をかけずに対応することができます。
入居後の光熱費、固定資産税、保険料、通勤・通学の交通費などを具体的に試算し、“引越し後の1年”を紙に書き出します。
ここまでのステップで見直した返済比率と生活の満足度が両立しているかを最終確認しましょう。
どうしても決め切れないときに、判断を後押しする考え方を最後に2つだけ紹介します。

毎月の家賃と住宅ローンの返済額を比較してあまり大差がない場合、住宅ローンの返済という支出の固定化による安心は大きな価値であると言えます。
長く同じ地域で暮らす予定があるのであれば、固定金利で返済額を確定させる、あるいは変動でも返済比率を抑えて余力を残すなど、“現状よりも安心できる設計”で進めていきましょう。
収入や勤務地が大きく変わる可能性が高いのであれば、まずは慎重に計画していきましょう。
緊急資金を積み増ししながら、建築費や物件の比較検討を続けます。この準備期間を置くことで選択肢の幅が広がり、納得できる家づくりにつながります。
金利の行方は専門家でも読み切れません。だからこそ、返済比率に余裕を持たせ、建築費の総量を整え、将来の維持費を見える化する、この3点を先に整えることが後悔のない家づくりの近道です。
賃貸の家賃が上がる局面では、住居費を固定化して暮らしの基盤を安定させることに価値が高まります。家庭の状況に合わせて、固定・変動のどちらを選ぶ場合でも、“余裕”を持たせた計画にしておくことを忘れないようにしてください。
最後に、家は「今」を良くするだけでなく「これから」の毎日を支える場所となるようにつくっていきます。
数字と暮らしのバランスを丁寧に整えながら、家族にとって納得のいく選択をしていきましょう。

私たちぽんたのいえは、「ただ家が売れればいい」とは思っていません。
創業は 1958 年、半世紀を超えて地元東三河の公共事業を担ってきました。
私たちがみなさまと共に作り上げてきた街。
住まわれている⽅が笑顔になるよう想いを乗せてお仕事をしてきました。
今ぽんたのいえで、⼾建のお家を建てているその理由も同じです。
『みなさまに笑顔で暮らしていただくため』
笑顔で暮らす、これほど素敵な毎⽇はありません。
⼀緒に夢の家づくりを始めましょう。
ぽんたのいえ3つのポイント
①ローコスト住宅なのに新築⾃由設計
②ローコストなのに安⼼で安全な適正施⼯期間
③建てた後の安⼼なアフターメンテナンス対応
ご相談お待ちしております。
ご連絡先
フリーダイヤル 0120-56-3948 (受付時間: 10:00~18:00)
お問い合わせフォーム
https://ponta-house.net/contact.php
